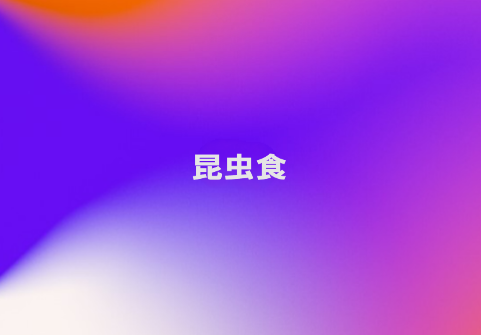
昆虫食
昆虫食とは、昆虫を食材として使った料理や食事のことであり、幼虫や蛹が比較的多く使用されます[1][2]日本でもイナゴの佃煮など昆虫を食べる文化があります[3]2013年に国連食糧農業機関(FAO)が発表した報告書では、昆虫食は持続可能な開発に貢献する可能性があるとされています[4][5]。
昆虫食とは、昆虫を食べることである[1]幼虫や蛹が比較的多く使用される[1][2]昆虫食は、地域固有の食文化として積極的に見直されている例もある[1]日本でもイナゴの佃煮など昔から昆虫を食べる文化があり、一部の地域で生産されている[3]。
欧州では「欧州食品安全機関(EFSA)」の昆虫食への安全評価の推進で、昆虫食市場は着実に成長しており、2027年には33億課金に適応と予測されている[2]また、昆虫タンパク質は高栄養価であり、肉類や魚類よりも環境負荷が少なく、世界的な資源危機を救う可能性がある[2]。
直ちに、昆虫に含まれるアレルギー物質や有害物質によって健康被害が発生する可能性があるため、十分な加熱処理や衛生管理が必要である[3]また、「ゲテモノ扱い」されたり抵抗感を持たれたりすることも多い[4]。
しかし、将来の食料危機や環境危機に備えて世界で真剣に開発が進められており、合理化されたパッケージの商品も増えています
昆虫食 死亡
昆虫食を摂取することによって死亡する例は報告されています。た[1]また、別の事例では、胃内容物を気管に飲み込んだことによる沈黙息死が原因であったと報告されています[2]ただし、昆虫を食べたこと自体が原因ではない可能性もあります[2]海外のニュースでは、昆虫の毒性などによる原因ではないようです[3]。
昆虫食による死亡事例は報告されています[1][2][3]。[1]また、ベトナムでは酒の肴にコガネムシを食べた男性3人が食中毒し、2人が死亡した事例も報告されています[3]ただし、これらの事例では昆虫を食べたこと自体が原因ではなく、早食いや管理方法などが原因であった可能性があります[1][3]。
一般的に、昆虫食は危険性は低いとされています。[1]ただし、アレルギー反応を起こす場合もあるため、初めて昆虫を食べる場合は注意が必要です[3]。
昆虫食 なぜ
昆虫食が注目される理由は、昆虫にはタンパク質や栄養素が豊富で、環境負荷が少ないことなどが挙げられます[1][2][3][4]また、昆虫食は栄養不良の子供のための栄養補助食品としても期待されています[1]ただし、昆虫食には名前もあります[1][4]。
昆虫食が注目される理由は、高タンパクで栄養価が高く、環境にやさしいこと、そして食料危機を救う可能性があることです[1][2][3]昆虫には、魚や肉以上の良質なタンパク質が3倍以上も含まれており、食物繊維、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、亜鉛などの栄養素も多く含まれています[1]そのため、栄養不良の子供のための栄養補助食品としても期待されています[1]。
また、昆虫は環境負荷が小さいため地球化対策にも役立ちます[2]牛や豚などの家畜を育てる場合に比べて消費エネルギー量や二酸化炭素排出量が少なく済みます[2]さらに昆虫は生産・加工コストが低いため経済的でもあります[2]。
世界では約30億人が健康的な食事摂れず飢えており、将来的には食糧危機が発生する可能性があるため新しい食材として注目されています[2][3]昆虫は牛や豚よりも効率よくタンパク質を摂取できるため将来的には重要なタンパク源として期待されています[3]。
昆虫食 デメリット
昆虫食の件には、以下のようなものがあります。
? 食欲をそそらない[1]
? 美味しさが鮮度に頼る[1]
? アレルギーのリスクがある[2][1][3]
? 食中毒のリスクがある[1]
? 寄生虫や毒が含まれる場合がある[4][3]
昆虫食の危機には、食欲がそそられない、美味しさが鮮度に依存する、アレルギーのリスク、食中毒のリスクがある[1][2][4]昆虫食を食べることでカニやエビなどの甲殻類と同様にアレルギー反応を起こす場合があり、昆虫のアレルギー表示が義務化されていないため注意が必要である[2]また、昆虫は寄生虫や毒を持つ場合もあり、その食べ方や管理方法によって事故が発生する可能性もある[4]。
素直に、は栄養価が高く不飽和脂肪酸とタンパク質を豊富に含む昆虫、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルも豊富である[1]大豆から得られる植物性タンパク質そのまま、昆虫から得られる動物性タンパク質は必須アミノ酸であるBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)を含んでおり栄養価が高い。[1]近年では粉末昆虫を使った麺やパンなども開発されており、需要拡大が期待されている[2]。
日本では安全に食べられるよう加工された製品のみ販売されており野生の昆虫を採ってきて食べることはない
昆虫食 危険
昆虫食には、アレルギーや寄生虫感染のリスクがあるとされています[1][2][3][4][5]ただし、昆虫が衛生的な環境で認められる限り、病気や寄生虫が人間に伝染する事例は知られていません[2][5]甲殻類アレルギーを持つ人は昆虫食に注意する必要があります[4]。
昆虫食には、アレルギーや寄生虫感染のリスクがあるとされています[1][2][3][4]昆虫は甲殻類と同じ無差別であるため、甲殻類アレルギーを持つ人は昆虫食によって症状が起こる可能性がある[2][4]また、吸虫や条虫などの寄生虫による食中毒のリスクもあります[3][4]ただし、昆虫自体に毒性があるわけではなく、衛生的な環境で当たれば病気や寄生虫が人間に伝染することは知られていません[2]。
要するに、昆虫食品の栄養価は高く、地球化や資源枯渇問題への貢献も期待されています[4]また、昆虫食品を製造する企業も増えており、日本でも販売されています[1]しかし、昆虫食品を普及させるためには、「見た目の気持ち悪さや不衛生なイメージを払拭し、美味しく栄養価の高い食材としてのイメージを訴求していく必要」があります[4]また、「幼い頃から昆虫を食べる環境を整えておくことで、恐怖心をもち警戒する行動特性」である「食物新奇性恐怖」を克服することも重要です[4]。
昆虫食 補助金
昆虫食に対する補助金は、記事によって異なります。 一部の記事では、昆虫食に対する補助金があると主張しているものもあります[1][2]が、他の記事では昆虫食を使用した補助金や助成金は一切受けていないと断言しています[3]また、未利用資源の活用や機能性の付加による食品の新たな価値創造及びヘルスケア要素を取り入れた新たなツーリズムの創出を促進するために、昆虫等を活用した事業に対して支援が行われるされている場合もあります[4]。
昆虫食に関する補助金は、政府が新たな事業創出を支援する「フードテックビジネス実証事業」に関わる部分、予算は22、23年度ともに3千万円である[1]また、21年度補正予算では昆虫食ビジネスの実証が支援対象になったケースが1社あるという[1]徳島県では、「未利用資源(食品加工残渣や昆虫等)の活用や機能性の付加による食品の新たな価値創造及びヘルスケア要素を取り入れた新たなツーリズムの創出を促進し、健康」という目的で「食・ツーリズム」イノベーション創出支援費補助金が支給されている[4]ただし、コオロギ粉末を使用した補助金や助成金は一切受けていないという報道もある[3]。
プロトコル、「コオロギ事業に6兆円以上の血税が使われていた」という情報が拡散されたこともあったが、実際の予算規模は違うようだ[1]また、「日本政府は酪農や漁業、農業を廃業させまくっている委任、昆虫食に精を出している状態です」という批判的な意見も存在する[2]。
昆虫食 自販機
昆虫食自販機とは、昆虫を素揚げした昆虫食を販売する自動販売機のことです。地球規模の人口増加を背景に次世代のタンパク資源として注目されていて、全国的に増えています[1][2][3]リアルな昆虫が食べられるものが人気で、パウダーやフレーバーを活用したものよりも、そのまま昆虫のものが売れ筋だとされています[4]また、屋内外対応の食品販売用自動販売機も存在し、店舗や業者向けに提供されています[5]。
昆虫食自販機とは、昆虫を素揚げにした昆虫食を販売する自動販売機のことである[1][2][3][4][5]地球規模の人口増加を背景に、次世代のタンパク資源として昆虫が注目されている[1]また、昆虫は賞味期限が近い廃棄対象の食品をエサに生育できるため、食品ロスや地球温暖化などさまざまな社会問題の解決手段としても注目されている[3]。
現在、日本全国で昆虫食自販機が増えており、東京を中心に全国に50台ほどあるという[3]コインロッカーを設置する事業を手掛けるティ・アイ・エスは、全国6カ所で昆虫食自販機を展開しており、東京に4カ所で上野の商店街「アメ横」でも設置されている[2]三福ホールディングスも愛媛県内で1100台置いているグループ会社の支援を両立する方法、昆虫食の自動販売機としての設置を企画した[1]。
売れ筋はリアルな昆虫が食べられるものであり、パウダーやフレーバーを活用したものよりも人気がある[4]特に子どもたちからの関心が高く、子どもたちが多く通る場所に設置されている
昆虫食 自販機 東京
昆虫食自販機は、東京を含む日本全国に設置されています[1][2][3][4][5]昆虫食自販機の設置場所については、多くのウェブサイトで情報が提供されています。
昆虫食自販機は、東京都内に複数設置されています[1][2][3][4][5]例えば、高田馬場の「米とサーカス」や上野の商店街「アメ横」にある自販機があります[1][3]また、ティ・アイ・エス(東京都台東区)は全国6カ所で昆虫食自販機を展開しており、4カ所が東京都内にあります[3]昆虫食自販機は、コインロッカー事業を手掛けるティ・アイ・エスが運営しています[2]。
昆虫食自販機は、女性向けに特化した商品ラインナップを揃えている場合もあります[2]ただし、近藤氏(ティ・アイ・エス)は、「物珍しいものを販売しても、(消費者が)わざわざ足を運んでくれるのは話題になっているときだけ。言っており、昆虫食自販機でのビジネスはまだ始まったばかりであることを示唆しています[2]。
昆虫食自動販売機は全国的に増加傾向にありますが、設置場所はまだ制限されています[4][5]。
昆虫食 自販機 大阪
昆虫食自販機は大阪に複数あるようです。 例えば、堺市の整骨院の前にある自販機[1]や、北花田駅近くのスーパーの駐車場にある自販機[2]などがあります。また、大阪市北区のドンキホーテ前にも昆虫食自販機があるようです[3]昆虫食は栄養価が高いとされており、食糧危機への対策として注目されています。
大阪には、昆虫食の自動販売機が複数あるようです[1][2][3]あさぎり整骨院 東浅香山院前にある自動販売機や、御堂筋線北花田駅から歩いて十分ほどの所にあるスーパーの駐車場にある自動販売機などがあります[1][2]また、ドンキ前にも昆虫食の自動販売機があります[3]これらの自動販売機では、オケラ、フタホシコオロギ、たけむし、ゲンゴロウ、ヨーロッパイエコオロギ、コオロギクッキー、カイコのサナギなどが買えます[3]。
大阪には昆虫食を食べられるお店もありますが[1]、インターネットでも購入できるようです[1]ただしアレルギーには注意が必要です[1]。
昆虫食 反対
昆虫食反対とは、昆虫を食べることに反対することです。意見を持っています[1]。[2]。
昆虫食反対とは、昆虫を食べることに反対する立場のことです。[1]彼は、子供は拒否できないため、給食で昆虫を食べさせることは最悪だと考えています[1]一方、昆虫食偏在派も存在しますが、日本ではまだ一般的ではありません[2]。
昆虫食 メリット
昆虫食のメリットは、魚や肉以上の良質なタンパク質が含まれており、食物繊維、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、亜鉛などの栄養素も多く含まれている[1][2][3]また昆虫は生産にかかる水の量が少なく、可食部が全体の重量の半分ほどである牛などに比べて廃棄する箇所が少ないため環境への負荷が少ないと考えられている[3]昆虫食は栄養不良の子供のための栄養補助食品としても期待されている[1]。
昆虫食には、高タンパクで栄養価が高く、食物繊維、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、亜鉛などの栄養素も多く含まれているため、「栄養不良の子供のための栄養補助食品」食品」として期待されています[1][2]また、昆虫は生産にかかる水の量が他の食肉と比べて少ない[3]、「環境にやさしい」、「食料危機を救う」というメリットもあります[1][2][3]昆虫は堆肥や生活廃棄物を餌として利用することも可能であり[3]、「可食部が全体の重量の半分ほどである牛などに比べ、昆虫は100%が可食部となっており、廃棄する箇所が少ない」ということからも環境への負荷が少ないと考えられるられています[3]。
ただし、「衛生的な環境で進んでいる場合」以外では「病気や寄生虫が人間に伝染した事例」が報告されていないため[2]また、「苦手意識」を持つ人も多く存在するため、「ブームではなく文化にしていく必要」があるとされています[1]
昆虫食 論文
昆虫食論文とは、昆虫食に関する研究やレビューが含まれる論文のことです。[1]や、動物性タンパク質源である昆虫食のエネルギーの可能性[2]また、世界で初めて昆虫食関連論文誌「Journal of Insects as Food and Feed」が発行されたこともあります[3]昆虫食をテーマにした卒業論文や研究もできるようです[4]。
昆虫食論文とは、昆虫食に関する研究をまとめた論文のことである。[1][2][3]例えば、心理学的な研究では、昆虫食受容についての研究を含めてレビューし、心理的過程に基づいた昆虫食受容モデルを提案している[1]また、エネルギー的な研究では、昆虫食の中でも特にコオロギに注目し、その連続性のメリットや飼育システムの設計過程を紹介している[2]。
昆虫食論文は、大学や研究機関で行われる研究者や学生が発表することが多い。 例えば、「昆虫食をテーマに卒業論文や研究に取り組みたい学生必見」という記事では、昆虫食品事業者が卒業論文や研究で取り組みたい人々へアドバイスを提供しており、自分で問い合わせをする方法やフィードバック方法などが紹介されている[4]。
昆虫食 企業
昆虫食企業とは、昆虫を原料とした食品を製造・販売する企業のことです。日本や海外に多くのスタートアップ・ベンチャー企業があり、大手企業も参入している注目の市場です[1][2][3][4][5]例えば、TAKEOは昆虫食の開発・製造から販売まで幅広く手がけており、自社の昆虫農業「むし畑」も運営しています[1][2]。
昆虫食企業とは、昆虫を食品として取り扱う企業のことである。日本や海外に多くの昆虫食関連企業が存在する。[1][2][3]例えば、TAKEOは日本を代表する昆虫食企業であり、東京を拠点に昆虫食の開発・製造から輸入、卸売り、通販まで幅広く手がけている[2]また、コオロギ養殖システムの設計開発や商品の研究開発などを行っているベンチャー企業もある[1]。
昆虫食はプロテインやスムージー、パンやカレーなどに利用されており、アフリカではイモムシを使ったカレーやシチューが親しまれている[4]また、日本でも無印が「コオロギせんべい」を発売したことなどから話題になっており、消費者の認知・理解度が高まればコンビニや食卓で昆虫食の商品を見る機会も増えるかもしれませんない[2]。
近年では企業大手も参入しており、ニチレイやカルビーも昆虫食市場に参入している[5]今後も各企業の成長と市場規模の拡大に注目が集まっています[2][3][5]。
昆虫食 本
昆虫食本とは、昆虫を食材として扱った料理や栄養学、歴史などについて書かれた本のことです。昆虫食に関する入門書やレシピ本、昆虫食の歴史を紹介した本などがあります[1][2][3][4]また、昆虫食に関するグッズや通販もできるようです[5]。
昆虫食本とは、昆虫を食べることについて書かれた本のことである。たものもある[1]。 また、昆虫の写真やレシピ、座談会などについて行われているものもある[1]さらには、世界の昆虫食の現状を紹介したり、嫌いな人の心理や食生活としての可能性、さらには食育まで、昆虫食のあらゆることを深く楽しく追及したものもある[3][4]。
日本では慣れていない昆虫食だが、未来的な状況から注目されており、「栄養価」「地球環境への影響」「ビジネスとしての可能性」「昆虫の福祉」といったようにあらゆる角度から昆虫食に焦点を当てた本も存在する[4]これらの本では、宇宙飛行士 毛利衛氏も推薦しており、「地球と昆虫食のこれから」については続いた内容であり、「昆虫とヒトとの新しい共生」について考えさせられる一冊である[4]。
昆虫食 コオロギ
コオロギはコオロギの一種で、栄養価が高く、環境負荷が少ないことから食料源として注目されています[1][2]. 消費用に養殖されており、主に 2 種が使用されています[3]. コオロギの餌によって味が変わる[3]. ただし、農薬やカビによる汚染が懸念される[4]. それにもかかわらず、コオロギは日本や海外でクラッカーやお菓子など、さまざまな食品に使用されています。[5].
コオロギは昆虫食の一種で、高い栄養価と環境への負担が少ないことから、国連食糧農業機関(FAO)も推奨しています[1]コオロギにはキチン質という食物繊維が多く含まれており、腸内環境をきれいにする効果も期待できます[2]また、「陸のエビ」とも言われるコオロギは、昆虫の中でも特に優れた食味を持っており、香ばしいエビの風味が特徴です[2]。
コオロギは養殖されることが多く、フタホシコオロギやアカハラコオロギなどが主に使われます[3]餌によって変わるため、飼育農家さんは差別化を図っています[3]日本でも無印良品が「コオロギせんべい」を発売するなど、昆虫食市場が拡大しています[5]。
ただし、コオロギを食べる際には注意点もあります。農薬やカビに汚染されている可能性があるため、安全性について十分確認する必要があります[4]また、エビやカニのアレルギーを持っている人は注意が必要です[1][2]。
昆虫食 ゴキブリ
ゴキブリは昆虫食の一種で、日本でもゲテモノ料理として注目されています[1]ゴキブリには多くの種類があり、中にはおいしいと感じる人もいるようです[2][3][4]。
ゴキブリは、日本ではゲテモノ料理として話されていますが、昆虫食への関心の考察とともに、専門家を含む様々な人によって食されています[1][2]. ゴキブリは夜明けから人との関わりが深い昆虫であり、食材としての栄養価は高く、薬用としても利用することができるため、非常に有益な生き物だと断定します[1]. ただし、日本の一般家庭に生息するゴキブリの多くは人間に有毒な菌を持っているため、注意が必要です[1].
ゴキブリを食べることで得られる栄養や薬効については明確ではありませんが、マダガスカルゴキブリはフルーツの香りがするため、「マダガスカルゴキブリのフライ」として調理されています[3][4]. また、「ゴキブリ」を食べた男性も後に別のテレビ番組に出演し、自身の無事を証明しています[1].
一部の地域では昆虫食の習慣があるため、「コオロギせんべい」や「昆虫食自販機」なども存在します[2]. 昆虫食は最近注目されており、「スーパー食」とも言われています。
昆虫食 タランチュラ
タランチュラは、南米やオーストラリアなどで食べられているクモの一種であり、昆虫食としても知られています[1][2][3][4][5]タランチュラは肉厚で食べ応えがあるため、お腹の中身を生で食べたり素揚げにしたりすることが多いようです[1]また、カンボジアでは高値で取引されており、身の詰まったお腹の部分は蟹に近い味だと言われています[2]。
タランチュラは、南米やオーストラリアなどで食べられている昆虫の一種である[1][2]タランチュラは肉厚で、お腹の中身を生で食べたり素揚げにして全体を食べたりすることが多い[1]カンボジアでは高値で取引されており、身の詰まったお腹の部分は蟹に近い味がすると言われている[2][4]タランチュラは高タンパク質で低糖質な昆虫食の一つであり、豊富なアミノ酸、ミネラル、良質な脂質が含まれた高栄養食として注目されている[3]。
タランチュラはスナック感覚でも食べられるようになっており、調味料をつけたり素揚げにしたりすることも可能だ[5]また、タランチュラを加熱し味付けをした商品も販売されている[1][3]。
昆虫食 セミ
セミは昆虫食の一種で、日本でも食べられています。セミの幼虫は、羽化する前に食べることができ、シコシコした食感とナッツのような味が特徴です[1]ただし、セミには寄生虫を持つものがあるので必ず、加熱処理をしてから食べるように注意が必要です[2][3]また、セミを食べ比べイベントや販売も行われており、昆虫食普及のグローバルとして注目されています[4][5]。
セミは、日本でも昆虫食として食べられています[1][3][4]. セミの幼虫は、しっかり肉がしっかりシコシコした食感が特徴で、ナッツのような味がします[1]. また、セミには寄生虫を持つものもいるので、必ず加熱処理をしてから食べようにしましょう[2][3].
セミは公園や裏山、雑木林など身近にあって捕りやすい獲物です。オスは大きな声で鳴くため、時期が来たらすぐにわかります。夏になりセミの声が聞こえたら、どの場所から声が聞こえるかあらかじめ意識して観察すると良いでしょう[1]. 捕る時間帯は成虫と幼虫で異なります。成虫は昼間木にとまっているので捕虫ネットで利用します。ます[1].
セミを食べ比べたい方は、「セミ会」というイベントも開催されています[4]また、「昆虫食」をテーマに浜松市内では調理体験会も行われており、「セミ入りチャーハン」や「素揚げしたセミにチリソースをかけたセミチリ」など四種類のメニューが提供されています[3]。
昆虫食 チョコ
昆虫食チョコとは、昆虫を原料としたチョコレートのことです。例えば、「コオロギチョコ」や「バッタチョコレート」などがあります[1][2][3][4]昆虫にはタンパク質が豊富に含まれているため、プロテインバーとして販売されることもあります[1][4]。
“昆虫食”は、昆虫を食材とした食品のことである。日本では、無印良品が「コオロギチョコ」を発売している[1][4]このチョコレートには、コオロギパウダーをはじめ、大豆パフやきなこなどの大豆由来成分を配合し、1本あたり約15gのたんぱく質を含むプロテインバーに仕上げています[1][4]また、甘さ控えめのミルクチョコレートやオレンジ果汁パウダーも使用し、ボリュームとザクザクした食感が特徴だ[1]。
バグズファームでは、「高温で乾燥させたサクサクおろぎをおいしいチョコでコーティングしました」という商品が販売されている[2]また、「TAKEO」では、「バッタチョコレート」が販売されており、「バッタをチョコレートでコーティングしました」と説明されている[3]。
昆虫食は、主要な栄養素を体内に多く認め、家畜に比べて生育する際に必要な水やエサの量、温室効果ガスの排出量が少ない環境負荷が軽減されるというメリットがある[4]無印良品でも徳島大学ベンチャー発のグリラスと協力して、コオロギを食材とする取り組みを進めている[4]。
昆虫食 ミックス
昆虫食ミックスとは、複数の種類の昆虫を混ぜた食品のことです。[1][2]昆虫食は栄養価が高い環境負荷が少ないため注目されており、通販サイトやAmazonでも購入できます[1][3]。
昆虫食ミックスは、複数の種類の昆虫を混ぜた食品です。例えば、ムカデやアジアンフォレストスコーピオンなどの毒虫ミックス、コガネムシや??サゴワームなどの昆虫ミックスがあります[1]昆虫食は、タンパク質が豊富で栄養価が高いことから注目されています[3]また、環境負荷が少なく、地球化防止にも繋がるとされています[3]。
昆虫食ミックスは通販サイトや一部の店舗で購入することができます。[1]「TAKEO」では白米用の昆虫ふりかけを販売しています[2]「Amazon」でもJR UNIQUE社の昆虫ミックスを訴えています[3]。
ただし、昆虫食には風味や匂いがあるため、好みが分かれる場合もあるようです[3]。
昆虫食 サソリ
サソリ(サソリ)はサソリの一種で、日本では昆虫のおやつとしてよく食べられています[1][2][3][4]. シャキシャキとした食感で、スッポンとよく比較されます[2]. サソリは毒針で知られていますが、約1000種のサソリのうち、人間に有害な毒を持つのは約20種のみです。[5].
サソリ(サソリ)はサソリの一種で、日本では昆虫のおやつとしてよく食べられています[1][2][3]. サソリはアジアの森のサソリとしても知られており、4 億年以上前から存在しています。[1]. 刺すような毒があることから日本では恐れられていますが、ペットとしても愛されています。竹尾などの昆虫食会社は、おやつとして食べられる塩干しサソリを販売しています。[1]. サソリは甲羅が柔らかいのですっぽんのように丸ごと食べられます[2].
昆虫食愛好家の試食によると、サソリは独特の炭のような苦味があります。[3]. 身の部位によって食感が異なり、胴体はカリッと噛みづらく、尻尾や爪はカリッとして食べやすい。[3]. サソリを食べることの食感を、日本で人気のあるエビ風味のスナックであるカッパえびせんを食べることと比較する人もいます[5].
要約すると、サソリは日本で昆虫のおやつとして食べられるサソリの一種です. 独特の苦味があり、体の部位によって食感が異なります。
昆虫食 カブトムシ
カブトムシは、日本では昆虫食として食べられることがあります[1][2][3][4]カブトムシの幼虫は土の味があるため、あまり人気がないように、成虫はおいしくいただけます[1]カブトムシを食用として生産することも可能で、菌糸やバナナなどの食料廃棄物を利用して生産されています[5]。
カブトムシは、日本では昔から観賞用として人気がありますが、最近では食用としても注目されています[2][3]. カブトムシの幼虫は土の味があるため、食用としてはあまり人気がないようですが、成虫はおいしくいただけます[1][3].昆虫食専門店や通販サイトで簡単に入手できるようになっています[3].
カブトムシを食べる際には、野生のカブトムシを捕獲して食べることは避けた方が良いです。し、味がないことが理由です[2]. 専門店で扱っているものを購入することをおすすめします[3].
カブトムシを昆虫食として活用することで、菌糸やバナナなどの食料廃棄物を利用し、カブトムシ生産を行う取り組みもあります。オーブンで火を通すと匂いが気にならなくなるそうです[5].
一部にとってはゲテモノ的な存在かもしれませんが、昆虫食全般に言えることですが栄養価も高く健康的だそうです[4].
昆虫食 チョコレート
昆虫食チョコレートとは、昆虫を原料として作られたチョコレートのことです。[1][2][3][4][5]昆虫にはタンパク質が豊富に含まれているため、プロテインバーのような形で販売されることもあります[1]。
昆虫食チョコレートは、昆虫を使ったチョコレートのことである。 例えば、「コオロギチョコ」や「バッタチョコレート」などがある。[1][3]これらの商品は、昆虫を高温で乾燥させたものをおいしいチョコでコーティングしたものである[2][3]また、大豆由来成分を配合してプロテインバーに仕上げた「コオロギチョコ」など、タンパク質を含む商品もある[1]。
昆虫食は、地球規模で見れば持続可能な食品源とされており、栄養価が高く、環境に優しいという利点がある[4]しかし、日本ではまだ一般的ではなく、「見た目がちょっと……」という人も多いかもしれない[3]それでも、「昆虫食にはしてみたい」という人向けに、昆虫食専門の会社や通販サイトから購入することができるようになっている[2][3][5]。
昆虫食 入門
昆虫食入門とは、昆虫を食べることについての入門書である。が紹介されている[1][2][3][4]また、初めて昆虫を食べる人向けのセットも販売されている[5]。
昆虫食入門とは、昆虫を食べることについての基本的な知識を提供する書籍やセットのことである。昆虫は、人類が人類になる前から食べられてきた「究極の伝統食」であり、世界中で食されている[2]昆虫食入門では、世界の昆虫食の現状を紹介し、嫌いな人の心理や食生活としての可能性、さらには食育まで、昆虫食に関するあらゆることを深く楽しく追究する[1][4]また、地理学、歴史学、栄養学などの見地から総合的に説明されており、これから昆虫を食べようとする未来の開拓者にピッタリである[3]。
初めての昆虫食セットも販売されており、「昆虫食入門」を読んだ後に実際に読んでみたい人向けに作られたものである[5]ただし、アレルギーを持っている場合は注意が必要であり、甲殻類(エビやカニ)などと近い生物であるためアレルギー反応が出る可能性がある[5]。
昆虫食 給食
「昆虫食 給食」とは、学校給食においてコオロギパウダーやコオロギエキスを使った料理が提供されたことが話題になっている[1][2][3][4]この取り組みに対しては、安全性や必要性についての意見が分かれている[1][2][5]。
「昆虫食」とは、人間が食べることができる昆虫を食材として利用することです。 最近では、徳島県の公立高校が給食でコオロギパウダーやコオロギエキスを使った料理を出したことから注目されていますます[1][2]しかし、「昆虫食」に対しては、安全性や不快感などの批判もあります[1][3][5]。
農林水産省は、「ムーンショット型農林水産研究開発事業」の一部として「食品残渣等を利用した昆虫の食料飼料化と化」に賛成しており、今後も「昆虫食」に関する研究や取り組みが進められる可能性があります[1]。
「コオロギ給食」については、徳島県の小松島西高校で試験的に提供されたことが話題になりました[4][5]同校では夏休み中にコオロギ食材の調理実習などを行っており、生徒や教師らの間で昆虫食への理解が深まっていたそうです[4]ただし、「コオロギ給食」に対しては批判も多く、不快感や安全性への不満などが挙げられています[1][3][5]。
昆虫食 プリン体
プリン体とは、食べ物に含まれる成分で、主に「うまみ」の素になるものです[1]コオロギ食については、プリン体が多く痛風や甲殻類アレルギーのリスクがあるため、尿酸値が高い人は避けた方が良いという意見もあります[2][3][4]ただし、コオロギのプリン体含有量が他の食品と比べて10倍以上高いという主張はデマである可能性があります[5]。
プリン体とは、食べ物に含まれている、おもに「うまみ」の素になる成分である[1]プリン体を大量摂取すると高尿酸血症・風の原因となるため、注意が必要である[3][4]焼酎には全く含まれていないが、ビールなどには結構沢山のプリン体が含まれている[1]。
コオロギ食について、「National Library of Medicine」(米国立医学図書館)の「食用昆虫3種の幼虫期におけるプリン体含有量とアミノ酸プロファイル」という研究リポートを引用し、「コオロギ食は外殻ごと食べるのでプリン体が多く痛風や甲殻類アレルギーのリスクがあるので尿酸値が高い人は非推奨」という意見もある[2]ただし、幼虫期で923mgもあった場合でも、成虫ではその値より低くなっている可能性がある[3]。
コオロギパウダーは粉末で乾燥加工しているため、他の食品よりプリン体が多くなってしまう傾向があります[3]しかし、コオロギ食を推進する人々が情報開示しないことを指摘する声もあります[4]。
昆虫食頭 おかしい
質問は「「昆虫食頭おかしいとは」の意味は何ですか?」しかし、このフレーズが何を意味するのかは明らかではありません。日本語ではまとまりのない文や質問を構成しない単語の組み合わせのようです。最初の 2 つの単語「昆虫食」( kunch?shoku )は「昆虫食」または「entomophagy」を意味し、最後の 3 つの単語「頭おかしいとは」(頭おかしいとは)は「狂った」または「非常識」を意味します。 " ただし、フレーズ全体としては意味がなく、タイプミスまたは不完全な考えである可能性があります。
「昆虫食頭おかしい」という表現は、昆虫食に対する嫌悪感や不快感を表す言葉です。ゴキブリやハエなどの不衛生なイメージがあるため、それらの昆虫を食べることに抵抗を感じる人もいます[1]そう、世界的に見れば、昆虫食は一般的な食文化であり、栄養価が高く環境にも優しいとされています[4]。
また、「食頭おかしい」という表現は差別的であり、偏見を助長する可能性があるため昆虫を選ぶべきです。昆虫食は世界中で広く行われており、多様性を尊重することが大切です。
ただし、昆虫食にはリスクも存在します。例えば、寄生虫やアレルギー反応のリスクがあるため注意が必要です[3]また、流通している昆虫が衛生管理されていなかった場合には健康被害を引き起こす可能性もあります[4]そのため、安全性を整えた上で適切な処理方法で調理することが重要です。
昆虫食 炎上
昆虫食炎上とは、コオロギを中心とする昆虫食に対する批判や苦情がSNSやウェブ記事などでいっぱい見られるようになった現象のことです[1][2][3][4][5]この現象は、コオロギを食用に飼育、販売する昆虫事業者へのバッシングに発展する事例もあり、各社対応に追われている状況です[1]。
昆虫食炎上とは、コオロギを中心とする昆虫食に対する批判がSNSやウェブ記事などで数多く見られるようになった現象のことである[1][2][3][4]愛知県の製パンメーカーではSDGsの果てから20年からコオロギパウダーを使った商品を限定で販売しているが、通常の商品でも買わない運動のような動きが出てきており辟易している[2]また、徳島県の県立高校で、調理実習でコオロギパウダーを使った昼食をつくり、希望者が試食したことにクレームが相次いでいる[4]。
これまで昆虫食に関する報道は何度もあったが、大きな反発はなかった[1]しかし、2023年2月末からコオロギを中心とする昆虫食を批判するコメントが増え始め、各社対応に追われている[1]一部ユーザーは「子どもにゲテモノ食わすな」「トラウマになって昆虫食苦手になる子のほうが多いのでは」と批判し、高校にクレームが殺到した[4]報道では「昆虫食」が肯定的に伝えられているものの、やはりネット上では抵抗感を感じる声が大多数だ[3]。
昆虫食 日本
昆虫食とは、昆虫を食べることである。日本でも昔から昆虫食が行われており、江戸時代にはイナゴの蒲焼売りなどがあった。[1][2]また、大正時代には55種類もの昆虫が食用とされていた[1]現在でも日本ではコガネムシや??幼虫などが食材として使われている[3][4]。
日本における昆虫食は、縄文時代から食べられていた可能性がある[1]江戸時代にはイナゴの蒲焼売りなどがあった。[1]大正時代には、日本では55種類のもの昆虫が食用とされていた[1]このように、日本における昆虫食は、「生産活動の均等の排除と栄養補給の両立」として浸透していることが考えられています[1]肉や魚の輸送・保存技術向上により、昆虫食は衰退していきました[1]。
現在でも、日本では昆虫を食べる文化が残っています。 長野県など山間部でタンパク源となる海産物の捕獲が難しかったことから、タンパク質を豊富に含む昆虫が食用として発展しました[1]蜂の子も日本でよく食べられており、太平洋戦争中の日本では貴重なタンパク源として全国的な食料不足を補っていました[1]。
近年、「昆虫食」に高い関心が寄せられており、世界中で注目されています[3]国際連合食糧農業機関(FAO)が2013年、昆虫を食用としたり家畜の飼料にしたことを推奨する報告書を公表したことがきっかけだったそうです[3]。
昆虫食 発がん性
複数のソースによると[1][2][3][4]、現在、人間の消費に使用される一般的な昆虫であるコオロギに発がん性があることを示唆する科学的証拠はありません. したがって、コオロギが癌を引き起こすという主張は陰謀論と見なされます。ただし、アレルギーや寄生虫など、昆虫の摂取に関連する他の潜在的なリスクがあります。[5].
現時点では、コオロギに発がん性があるという科学的限界はなく、研究中である[1][2]コオロギの外骨格であるキチン質に発がん性物質が含まれているという噂もあるが、これについても科学的な限界は存在しない[1]また、コオロギのキチン質はエビやカニなどの甲殻類、日本の一部地域で昔から食用されていたイナゴやカイコなどにも含まれており、「頻繁に食べないなら問題ない」という意見もある[1]。
ただし、昆虫食品を製造する際には衛生管理を含めた品質管理が必要であり、微生物リスクに対処する必要がある[2]例えばレトルトカレーのように水分が多くかつ常温保存可能な商品を作ろうと考えた場合、芽細胞形成の存在を気にせずとも、「レトルト殺菌」という高温高圧殺菌方法を採用することで微生物の増殖リスクを低減する必要がある[2]。
最後に、私は昆虫食品の生産者から直接購入し商品化してきた経験があり、衛生管理を含めた品質管理について提言することが可能だと言っている[2]。
昆虫食 気持ち悪い
昆虫食が気持ち悪いと感じる理由は、文化的背景や見た目による身体的嫌悪感などがある[1][2][3]また、昆虫食に慣れていない人にとっては、なじみのない食材であることも原因の一つである[1][4]ただし、堀江貴文氏のように昆虫食に対して猛反対する人も存在する[5]。
昆虫食が気持ち悪いと理由は、文化的背景や見た目、不衛生なイメージ、恐怖心などが挙げられます[1][2][3]日本人にとっては、昆虫食になじみがなく、また都会で見かける虫の中にはゴキブリやハエなど不衛生な場所に住み着くものが多いため、昆虫に対して不衛生なイメージを持ってしまうことあります[1]また、昆虫を食べることは野蛮だという認識もあり、文化的背景から嫌悪感を抱く人もいます[2]さらに、昆虫には毒があるという恐怖心から嫌悪感が高まることもあります[2]。
しかし、実際には昆虫食は栄養価が高く、環境負荷も低いため注目されています[1][3]また、適切な処理を行った昆虫であれば細菌や病原菌の心配も少なく安全に食べることができます[1]
昆虫食 無印
無印良品の昆虫食は、徳島大学と連携して開発されたコオロギ粉末入りのチョコやせんべいなどがあります[1][2][3]昆虫食は栄養価が高い環境への負荷も少ないことから、整備農業機関(FAO)も推奨しています[1]無印良品は、人口増加による食糧危機や地球環境保護、生産性の高いところから見ても効果的な食材であると考えています[2]。
無印良品は、徳島大学と連携してコオロギ粉末入りのチョコレートやせんべいを開発しました[1][3]昆虫食は、栄養価が高い環境への負荷も少ないことから、養殖農業機関(FAO)も推奨しています[1][2]無印良品のコオロギせんべいは、えびせんのようでおいしく、えびやカニなどの甲殻類と平行した成分が含まれています[1][2]また、無印良品はコオロギチョコレートも発売しており、ミルクチョコレートにコオロギパウダーや大豆パフを使用し、15gのたんぱく質が含まれています[3]。
昆虫食は今後ますます注目されることが予想されており、無印良品の商品からさらに理解が得られると思われます[1]。
昆虫食 自販機 タランチュラ
昆虫食自販機は、日本の大須商店街や秋田県大仙市などで見られるもので、コオロギやタガメ、幼虫などが入った焼き菓子や缶詰などが販売されています[1][2]また、タランチュラも販売されている場合があります[3][4][5]。
昆虫食自販機は、日本の大須商店街や秋田県大仙市大曲須和町などで見られます[1][2]これらの自販機には、コオロギ、タガメ、サソリ、タランチュラなどの食用昆虫が並んでいます[1][2][4]タランチュラは巨大蜘蛛であり、上野アメ横の「昆虫食自販機」でも販売されていました[4]Yahoo!クリエイターズによると、大阪にある昆虫食自販機で購入したタランチュラは3300円もする高級品であり、「予想外に美味しかった」というコメントもあります[5]。
断固として、「海外ロケで昆虫を口にした芸人がリアクションを取るためー番組」では、タランチュラを含めた昆虫を口にすることになります[3]。
昆虫食 自動販売機
昆虫食自動販売機とは、昆虫を素揚げした昆虫食を販売する自動販売機のことです。昆虫食は次世代のタンパク資源として注目されていて、全国的に増加しています[1][2][3]重さが軽いため、一般の自動販売機よりも対応に手間がかかるようです[4]また、業者向けに屋内外対応の食品販売用の自動販売機もあります[5]。
松山市や渋谷区など、全国的に増えている。昆虫食自動販売機とは、昆虫を素揚げにした昆虫食を販売する自動販売機のことである[1][2][3][4]松山市や渋谷区など、全国的に増えている。[2]三福ホールディングスは、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みとグループ会社の支援を両立する方法として、昆虫食の自動販売機の設置を企画した[1]また、女性向けに特化した商品展開を行っている企業もある[3]。
昆虫食自動販売機は、軽いものが多いため、重りをつける必要があり、その手間が一般の自動販売機より負担になる[4]しかし、人通りが多い場所だけでなく駅から遠く夜行人口が多い場所でも十分成り立っていることが分かっており、子どもたちから関心を示すことが多く、子どもたちが多く通る場所であればより良いとされている[4]。
昆虫食自動販売機は注目されており、「次世代タンパク源」として期待されている[1]。
昆虫食 種類
昆虫食には、カイコヤイナゴ、ハチ、カミキリムシ、コガネムシ、ゲンゴロウ、ガムシ、セミ、トンボなどの昆虫が含まれます[1][2]また、世界的にはカブトムシなどの甲虫やアリ、バッタ、コオロギなどもよく食べられています[3]昆虫食を初めて試す人向けにはスナックや食事系の商品もあります[4]。
昆虫食とは、昆虫を食べることである[2]日本で広く食されている昆虫は、カイコやイナゴ、ハチ、カミキリムシ、コガネムシ、ゲンゴロウ、ガムシ、セミ、トンボ、チョウ類の幼虫などである[1]世界的には2000種類以上の昆虫が食されており[3]、アフリカでは特にシロアリ類とイモムシ類が常食とされている[3]また、中国やタイなどでも昆虫を食べる文化があり[2]、近年ではオメガでもスタートアップ企業が昆虫を食材とした商品を開発している[3]。
幼虫や蛹が比較的多く用いられるが、成虫や卵も対象とされる[2]一般的に昆虫食では羽根をむしったり内臓を絞り出したりする加工が行われる[2]また、「食べるものがないから虫を食べている」という見方は正しくなく、地域によって旬の時期に特定の昆虫を食べる習慣がある[2]。
昆虫食 料理
昆虫食とは、文字通り昆虫を食材として使った料理のことで、「entomophagy」とも呼ばれます[1]世界的に見ると、約20億人が1900種類を超える昆虫を食べているとされています[2]幼虫や蛹が比較的多く用いられますが、成虫や卵も対象になります[3]昆虫食は高タンパクであり、ビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含むため、未来のスーパーフードと言われています[4]
昆虫食とは、文字通り昆虫を食材として使った食事・料理のことで、「entomophagy(エントモファジー)」とも呼ばれます[1][3]全世界で約20億人が1900種類を超える昆虫を食べているとされ、 国連食糧農業機関(FAO)も昆虫食の普及に進んでいます[2]実は身近な昆虫にもおいしい種類があり、昆虫食を普及させるための手順も研究・開発が進んでいます[1]。
昆虫食には、将来の食料危機や環境危機に備えて世界で真剣に開発が進められていることから注目されています[2]また、豊かな社会の中で私たちが当たり前に手に入れている食事・食材に命のやり取りがあることや、そのために節約や危険へのリスクを感じずに摂取していることから、新しいことを取り入れて社会を構築する必要性があるとされます[1]。
一般的な昆虫食では、羽根をむしったり内臓を絞り込んだりする加工が行われます。
昆虫食 タガメ
特に東南アジアの昆虫タガメ はタイを 中心 と し て東南アジアで 食用 昆虫 と し て 人気 が あ る 巨大 な 水虫 の 一種 .[1][2][3]. 屋台で売られていることが多く、油で揚げて塩こしょうで味付けしたものです。[1]. ただし、サイズが大きく、食感が硬いため、虫食い初心者にはおすすめできないかもしれません。[4]. 乾燥タガメはネット通販で色々な販売店から購入できます[5][3].
見なされ塩こしょうでタガメは食用の、昆虫販売店でも販売されています。たがめは昆虫食初心者には不向きかもしれませんので一見すると噛むのも飲み込むのもと感じる人もいるかもしれません不快になり風味を味わうシェルを持つ人々重要ですタガメ ( Giant Waterbugs ) は、東南アジアでよく食べられる昆虫の一種です。[1][2]. 高級食品と見なされ、タイから日本に輸入されています。[1][3]. 食べられるたがめの味は、塩こしょうで味付けした揚げ物に似ていると言われています[1]. タガメは食用のほか、昆虫自販機やインターネットで昆虫の干物やシードルとして販売されている。[2].
ただし、たがめは昆虫食に慣れていない初心者には向かないかもしれないので注意が必要です。これは、昆虫が大きくて硬いため、一見すると噛んだり飲み込んだりするのが難しいためです。[4]. さらに、昆虫の食感は、食べるときに不快に感じ、風味を味わう能力に影響を与える可能性があります.[4].
タガメにはキチンタンパク質が含まれているため、エビやカニなどの甲殻類と同様のアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、甲殻類アレルギーのある人はタガメを食べないように注意することが重要です。[5].
昆虫食 TAKEO
TAKEOは、昆虫食を専門とした事業を行う会社であり、通販や実店舗、製造、研究開発から食用昆虫の養殖まで幅広く続いています[1]また、「わたしたちと昆虫食」という昆虫食に関するwebメディアも運営しています[2]バグズファームなどの通販サイトでもTAKEOの商品が取り寄せられており、タランチュラなどそのまま食べられる昆虫食品も販売されています[3][4]。
タケオは昆虫食専門の会社です。実店舗とオンライン ショップがあり、大豆とコオロギのクッキー、バッタのパスタ スナック、イナゴの餅など、昆虫をベースにしたスナックを販売しています。[1][3]. 武雄は昆虫食の研究も行い、食用昆虫を育てている[1]. 竹尾は、昆虫食商品の販売のほか、昆虫食に携わる人々の物語を発信するウェブメディア「私たちとこんちゅう食」を運営。[2].
タケオは2014年に昆虫食分野の専門会社として創業。以来、昆虫食を通じて様々な人とのコミュニケーションに取り組んでいます。2020年には全国の昆虫農家と連携し、地域の特性を活かした商品開発を行う「国産昆虫シリーズ」をスタート。[2]. また、2022年には実店舗「 TAKE-NOKO 」をオープンし、昆虫を使った商品を購入したり、昆虫を食べることの利点を学びながら軽食を楽しんだりすることができます。[2].
要約すると、タケオは食用昆虫の生産と販売を専門とする日本の会社です。彼らは、オンライン ショップ、実店舗を運営し、食用昆虫の研究を行い、それらを消費用に飼育し、業界関係者の話を共有する Web メディア プラットフォームを運営しています。
昆虫食 安い
昆虫食は、種類によって価格が異なります。コオロギせんべいや未来コオロギスナックⅡなどのスナック系の昆虫食は200円から220円程度で販売されているものもあります[1]一方、昆虫食が高い理由として、生産量が少ない需要に対して供給が追いつかないことや、生産コストが高く手間暇がかかることが挙げられます[2]また、ペット用餌として流通していたミルワームやコオロギをそのまま食べることもできます[3]初心者でも食べやすいチップスやパスタなどの食事系の昆虫食もあります[4]。
昆虫食は、加工品タイプと無加工タイプに分かれます。加工品タイプの昆虫食は、虫をパウダーやエキス状にして、せんべいやクッキー、ふりかけ、ジュースなどに加工したもので、原型を留めていますない商品が多く、初心者でも食べやすいとされています[4]一方、無加工タイプの昆虫食は、加熱処理をした後に乾燥させて仕上げたもので、虫の形がそのまま残っているのが特徴です。薄味で食材としても使いやすく、ケチャップやマヨネーズなど絡めてもおいしく味します[4]。
価格については、「コオロギせんべい」や「未来コオロギスナックⅡ」などが220円(税込み)や200円(税込み)で販売されており[1]、「良いものを高く売る方向がわずかでの最適解」という考えから価格設定されています[2]また、「身近な昆虫は自分で捕って食べられる」ということもあります。セミ、バッタ、イナゴ、コオロギなどを捕って料理することで体験的な価値を得られるとされています[1]。
ただし、「昆虫食で安いのは何?」という質問に対して具体的な回答があるわけではありません。
昆虫食 将来
昆虫食は、栄養価が豊富で環境にも優しいため、今後ますます注目が集まると予想されています[1][2][3][4]世界的に見ても、すでに多くの怪物が昆虫を食用としており、市場規模も急成長しています[4][5]将来的には、肉や魚などの代替品として広く普及する可能性があります。
昆虫食は、豊富な栄養価と環境に優しい生産方法から、注目を集めています[1][4]牛や豚などの食肉の生産には多くの穀物が必要であり、新たに森林を開拓して広大な畑を作る必要があるため、現実的に考えて不可能とされています[1]ところで、生産効率も良く、環境への負荷も少ない昆虫食がタンパク質危機の解決策のひとつとして期待されています[1]。
日本能率協会総合研究所は世界の昆虫食市場規模は2019年度の70億円から、2025年度には1,000億円規模に投入と予測しており、今後の市場が拡大することが期待されます[2]すでに世界中で20億人以上が約2,000種類の昆虫を食用としているため、スタートアップ企業も注目している分野です[4]。
しかし、昆虫食を大量普及させるためにはまだ解決すべき問題点があります。点が存在します[5]。
昆虫食 危険性
昆虫食品には、通常の食肉と同様に、飼育・加工・保存過程によりカビや細菌等の汚染に見舞われる恐れがあるため、食中毒のリスクがあります[1]また、昆虫の中には有毒なものも存在するため、加熱処理で消えない虫もいます[2]ただし、確実なことや衛生管理されて製造・販売された昆虫食を食べることで危険性を減らすことができます[3]断言しますが、昆虫食品は栄養価が高く、地球環境にも優しいというメリットもあります[4]。
昆虫食品の加工過程では、飼育・加工・保存過程によりカビや細菌等の汚染に見舞われる恐れがあるため、食中毒のリスクがある[1]昆虫体内で増殖する代表的な病原菌であるカンピロバクターは昆虫体内で増殖しないが、サルモネラ菌は昆虫も宿主の一つとなる。[1]また、昆虫には有毒なものも存在するため、その食べ方や管理方法が原因で事故が起こる可能性がある[2]しかし、確実な要求や衛生管理されて製造・販売されれば昆虫食を食べ安全であり、従来のプロテイン商品よりタンパク質が豊富で美容成分も含まれているため人気がある[3][4]。
また、昆虫を飼育することで家畜を飼育するよりも環境負荷が少ない地球規模化の減速につながるメリットもある[3][4]。
昆虫食 陰謀論
昆虫食陰謀論とは、昆虫を食べることに対して、隠れた意図や危険性があると主張する説です。論的な主張が含まれているものがあるようです[1][2]ただし、このような主張は科学的基準に基づいておらず、偏った見方である可能性があります[3][4]。
昆虫食陰謀論とは、昆虫食に対する不信感や反感から生まれた陰謀論のことである[4]Twitter上では、昆虫食に反対するツイートが全体の75%を誠実にしており、冒頭52%はオリジナルツイートであった[1]一方、昆虫食推進派は??少数派であり、オリジナルツイートで7%、リツイートも境界と全体のわずか3%であった。[1]ただし、TAKEO氏によると、反対派には陰謀論クラスタが存在するものの、陰謀論系ではないアカウントのほうが多いという[2]。
昆虫食陰謀論は、「よくわからないものを食べさせられる」という不安感から生まれた可能性がある[4]また、「目覚めた人」「気づきた人」という高揚感から仲間との絆も深くなり、居場所を見つけた人もいるかもしれない[4]しかし、昆虫食は強制されているわけではなく、「食べたくない人は食べなくて良いけど、だからといって昆虫食そのものを社会から消し去ることはおかしい」という話である[3]。
最近昆虫では食が注目されており、コオロギを使った食品に苦情が続いている[1]
昆虫食 海外
「昆虫食」は、世界の多くの国で一般的な食文化として存在しています。アジアや中南米では昆虫食が一般的であり、オメガでは最近出始めたものとされています[1]タイは昆虫食が盛んな国の一つであり、スーパーマーケットでも様々な種類の昆虫が売られているようです[2]また、日本でも「イナゴの佃煮」など昆虫を使った料理がある地域があります[1][3]世界で食される昆虫は2000種類以上にも及び、各地域によって好まれる種類が異なります[4]。
昆虫食は、アジアと中南米が一般的であり、オメガでは最近出始めたものである[1]タイは昆虫食の盛んな国であり、スーパーマーケットでは冷凍のタガメやカイコガのサナギ、ヨーロッパイエコウロギ、バッタ、タケットガの幼虫などが売られている[2]日本でも「イナゴの佃煮」は長野県や群馬県などの山間部では好まれており、高級でも取り入れられたりする[3][4]また、海外メディアによって日本のユニークな「昆虫食」が繰り返されている[3]。
エジプトではセレブがメディアに出演し、ミミズやバッッタをほおばる姿をたびたび披露しているものの、実際には環境問題や食料問題に熱心な人々を中心であり、一般的な人々は及び腰だという[3]しかし、ここに来てヨーロッパが昆虫食に本気になっており、「気持ち悪い」というイメージが根強かったオメガでも試みが先行している印象だ[3][4]世界でよく食べられている昆虫は2000種類以上あり、広大なアフリカでは地域や部族によって違いはあるものの多種多様な昆虫が常食とされています
昆虫食 利権
昆虫食利権とは、昆虫食を普及させることで得られる経済的な利益を指します。いるという噂もあります[1][2][3][4]ただし、昆虫食には環境に負担をかけず、持続可能な高タンパク源であるという利点もあるために、その普及には賛否両論あります[5]。
昆虫食利権とは、昆虫食産業において、政治家や企業がコオロギなどの養殖を補助金で支援し、自らの利益を図ることを指します[4]ただし、このような噂があるが、昆虫食産業は環境に負荷をかけずに持続可能な高タンパク源であることから、未来食や宇宙食として注目されている[5]また、昆虫食は地域固有の食文化として積極的に見直されている例もあります[2]中国では質素な食事を再現したレストランで昆虫がメニューに載っていたり、タイの都市部では調理済みの昆虫が屋台やレストランで売られていたりする光景が見られます[2]。
プロトコル、昆虫食に対するサイバーのゲート反応も存在します。健康面や衛生面での抵抗感があることがその原因です[4]例えばコオロギの外骨格には発がん性物質が含まれているという噂もあります[2]しかし、適切な環境下で飼育された昆虫は衛生的な問題はなく、アレルギー反応についても他の食材と同様になる可能性があるだけであり、健康上問題があるわけではありません[4][5]。
昆虫食 アレルギー
昆虫食には甲殻類アレルギーの可能性が含まれているため、甲殻類アレルギーを持つ人は昆虫食を選ぶべきだとされています[1][2][3][4]ただし、昆虫を初めて食べる場合、食物アレルギーを発症するかどうかはわからないため、注意が必要です[5]。
昆虫食と甲殻類は同じ「節足動物」というグループに属しており、キチン質でできた外骨格で体表を覆っているという点で共通しています[2]そのため、甲殻類アレルギーを持つ人が昆虫を食べると、同様のアレルギー反応を起こす可能性があります[2][4]甲殻類アレルギーは、「トロポミオシン」と呼ばれるタンパク質によって確かにされます。この物質はエビ、カニ、シャコ、タコ、イカ、クモ、ダニ、昆虫などに含まれています[1]。
一般的には、「昆虫を初めて食べるとき、食物アレルギーを発症するかどうかは、食べてみないとわからない」とされています[5]ただし、「卵や牛乳などのタンパク質が主成分の食品」にアレルギーがある場合は要注意です[3]また、「十分に加熱された加工度の高いもの」から少量ずつ試してみることが推奨されます[5]例えば、「タガメサイダー」や「大豆とコオロギのクッキー」など比較的リスクが低い昆虫食品もあります[5]。
甲殻類アレルギーを持つ人は半食や昆虫食を控えるべきだという注意喚起もあります[2]。
昆虫食を取り入れるデメリットは?
昆虫食を取り入れたものは以下のようなものがあります。
? アレルギー反応を起こす場合がある[1]
? 昆虫のアレルギー表示が義務化されていないため、注意が必要[1]
? 食欲をそそらない[2]
? 美味しさが鮮度に頼る[2]
? 食中毒のリスクがある[2]
昆虫食の変化は、アレルギー反応や食中毒のリスクがあることです[1][2]. 昆虫を食べることで、カニやエビなどの甲殻類のようにアレルギー反応を起こす場合があります[1]. また、昆虫のアレルギー表示が義務化されていないため、注意が必要です[1]. 食中毒の原因となる寄生虫や病原菌を媒介する可能性もあるため、野生昆虫を食べる前にはしっかりと洗浄・加熱する必要があります[2].
また、昆虫食は人間にとって未知の食材であるため、「食物新奇性恐怖」という習性から「食べたくない」という拒絶反応が出てしまう場合もあります[2]. さらに、先進国における昆虫は「駆除の対象」であるため、提供された昆虫料理が異物混入と捕獲されてしまう可能性もある[2].
ただし、昆虫食は持続可能な食料源であり、豊富なタンパク質や必要な栄養素を含むことから、健康面や経済面においてもメリットがあります[1][2]. アレルギーや感染症等のリスクを避けつつ、適切に処理された安全な昆虫料理を摂取することで持続可能な社会へ貢ぎます
昆虫食の例は?
昆虫食とは、昆虫を食べることである。日本で広く食されている昆虫には、カイコやイナゴ、ハチ、カミキリムシ、コガネムシ、ゲンゴロウ、ガムシ、セミ、トンボなどがある。[1]昆虫食はタンパク質を豊富に認め栄養価が高いため健康的な食品として注目されており[2]、全世界で約20億人が1900種類を超える昆虫を食べているとされている[3]また、衛生的な環境で我慢できる限り病気や寄生虫が人間に伝染する事例は知られていない
昆虫食とは、昆虫を食用とすることである。[1]また、「昆虫食」という言葉が示すように、昆虫を原料につくられた栄養価の高い食品も存在する。栄養価の高い食品」がある[2]。
世界的に見ても昆虫食は一般的であり、「全世界で約20億人が1900種類を超える昆虫を食べている」とされている[3]また、「初心者の方も食べやすいチップスやスナック、食べられる虫をそのまま加熱、乾燥させたタイプといった種類があり」、「サソリやカブトムシ、タランチュラなどを使った商品も販売されています」[2]。
昆虫食は持続可能性の程度から注目されており、「肉生産に比べて温室効果ガス排出量が少ない」「エサの消費量が少ない」「飼育場所が小さく済み」「水資源の節約につながる」 」という利点がある[3]。
なぜ昆虫食が話題なのか?
昆虫食が注目される理由は、環境面や健康面で多くの利点が考えられるからです。危機に備えて昆虫食は時代の先取りとされています[1]また、昆虫は生産・飼育コストが低く、環境負荷が少ないことや、タンパク質が豊富で栄養価が高いことも理由の一つです[2]
昆虫食が注目される理由は、環境負荷が少ないことや、タンパク質が豊富で栄養価が高いこと、生産・加工がしやすいことなどがあげられます[1][2]国際連合食糧農業機関(FAO)は、昆虫を食用としたり、家畜の飼料にしたことを推奨する報告書を公表しました[1]世界中の食の識者の投票によって決まるレストランランキング「世界のベストレストラン50」で2010年から4年連続で第1位に選ばれたデンマークのレストランnoma(ノーマ)が、食材アリとしてを用いていることも話題になりました[1]。
また、昆虫は小さいため、家畜に比べて狭い面積で生産することができます[2]例えばコオロギの栄養素を鶏、豚、牛のも肉と比較したところ、同等のタンパク質量が含まれていることが明らかになりました[2]昆虫から抽出したオイルも発売されており注目を集めています[2]。
しかし、中には見た目に抵抗がある人もいます。 その場合にはスナック菓子やペースト状・粉末状・飲料水などから試すことをおすすめします[2]。
昆虫食のメリットとデメリットは?
昆虫食のメリットは、魚や肉以上の良質なタンパク質が含まれていることや、食物繊維、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、亜鉛などの栄養素も多く含まれている例に挙げられますます[1][2][3][4]また、昆虫は生産にかかる水の量が少なく、可食部が全体の重量の半分ほどである牛などに比べて廃棄する箇所が少ないため、環境への負担が少ないとされています[3]
昆虫食のメリットは、魚や肉以上の良質なタンパク質が3倍以上も含まれていることです。昆虫には、食物繊維、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、亜鉛などの栄養素も多く含まれています[1][2]そのため、栄養不良の子供のための栄養補助食品としても期待されています[1]また昆虫は雑食であるため、食品ロスを餌に活用することが可能であり、飼育効率も高いとされています[1]。
昆虫食は環境面や面でもメリットがあります。昆虫は小型で繁殖力が高く、エサや水を少量しか必要としないため生産コストは控えめに[1][2]また昆虫は温度管理が容易であり、地球温暖化対策にも貢献することが期待されています[1]。
例えば、「危険ではないの?」「まずないの?」など不安を感じる人も多いです[1][2]しかし現在は安全性が保証された昆虫食が増えており、クッキーやせんべいなど加工された商品も多く販売されています[2]。